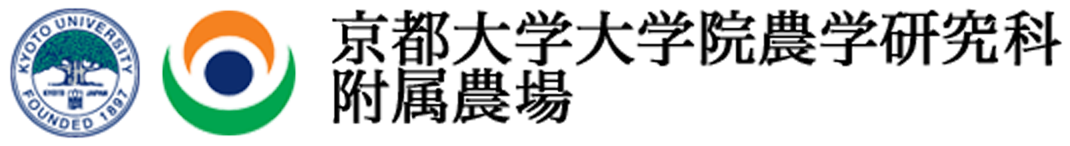研究活動
研究内容の紹介
教授 中野 龍平
モモの熟期の決定および老化機構の解明

モモは商業的に重要な作物であるが、一般に棚持ちが悪く、その改善が強く求められています。モモは成熟に植物ホルモンエチレンが関与するクライマクテリック型の果実に分類されます。クライマクテリック型の果実では、成熟の開始のみならず、過度の軟化や老化の進行にもエチレンが関与しており、棚持ち性には、果実自身のエチレン生成能とエチレンにより果肉が軟化・崩壊する反応性の二つが大きく影響します。これまでに、晩生希少品種に着目し、成熟開始時期、棚持ち性、エチレン生成・応答性、軟化特性に特徴的な品種を発見しています。本研究では、モモにおける熟期や老化に関わる生理的・遺伝的解明を目的とし、これらの品種や系統を遺伝資源として活用した解析による原因となる候補因子の探索を試みています。
カンキツの無核性に関する研究

カンキツは世界最大の果樹産業であり、無核(種なし)性は重要な育種目標の一つです。安定した無核果実は、雌性不稔性や種子の早期発育停止の形質に起因しますが、我が国在来の有核の紀州ミカン(’平紀州’など)の変異系統である’無核紀州’は早い時期に胚が発育を停止して、すべての種子が発達しない(Aタイプ種子)ことが明らかとなりました。’無核紀州’をブンタンと交配するとその後代に無核と有核が3:1に出現することが知られており、無核性ブンタン新品種が育成されています。しかし、胚の発育停止が高温により解除されることが分かり、温室栽培などにおいて問題となります。そこで、本研究では、’無核紀州’およびその後代の無核品種・系統の無核性発現について、胚の早期発育停止の機構解明および高温による発育停止解除の原因究明や防止技術の開発に取り組んでいます。
助教 長坂 京香
ハイブッシュブルーベリーの交雑組み合わせと果実発達に関する研究

ハイブッシュブルーベリーの栽培では、混植により他家受粉を促進することが推奨されています。他家受粉処理をした果実は、自家受粉処理と比べて成熟種子を多く含む場合が多く、果実サイズの増大を図ることができます。これまでに、交雑組み合わせにより着果率、果実サイズおよび果実生育期間が変化すると報告されていますが、その詳細なメカニズムはわかっていません。そこで、本研究では、花粉親が果実サイズおよび果実品質に及ぼす影響、および花粉親がもたらす果実発達差異の要因を明らかにすることを目的として研究を行っています。様々な交雑組み合わせにより人工授粉試験を行い、果実品質の評価をすることで、果実品質を向上させ得る花粉親の選定が可能となります。また、果実発達の経時的観察、およびトランスクリプトーム解析により、差異をもたらす原因解明に取り組んでいます。
助教 牧 隆宏
種なしトウガラシの原因遺伝子CKI1の機構解明とその利用による無種子果菜類の開発

果実作物において、種なし性は食べやすさや調理しやすさの点で消費者から好まれる。また、加工しやすさや廃棄物削減という点で産業的にも需要が高い。しかし、果実の種なし化をもたらす遺伝資源は限られており、様々な植物に利用可能なターゲット遺伝子も知られていない。我々はトウガラシの種なし変異体の解析から種なし化遺伝子を同定した。この遺伝子は植物に保存されており、トウガラシ・ピーマン類だけでなく他の果実作物へ応用できるのではないかと考えている。そこで、ゲノム編集を用いて変異を導入することで実際に種なし果菜類の開発を試みている。また、種なし果実は小さいことが品種作出の上で問題となるが、それを克服する果実大型化遺伝子の探索も行っている。
助教 村田 和樹
コムギにおける遺伝的組み換えの研究

ムギ類では、遺伝的組み換えが主にサブテロメア領域で起こり、動原体近傍ではほとんど発生しない。しかし、赤カビ病耐性遺伝子や収量に大きく影響するQTLなど、育種にとって重要な遺伝子が動原体近傍に存在する。そのため、これらの遺伝子の正確なマッピングや育種への活用が難しくなっている。本研究では、6倍体であり、染色体部分欠失系統を利用できるコムギを対象に、動原体近傍で遺伝的組み換えを誘発する方法を探る。そして、動原体近傍にある遺伝子マッピングとともに、遺伝的組み換えの制御メカニズムの一端を解明することを目標としている。